本ページはプロモーションが含まれています
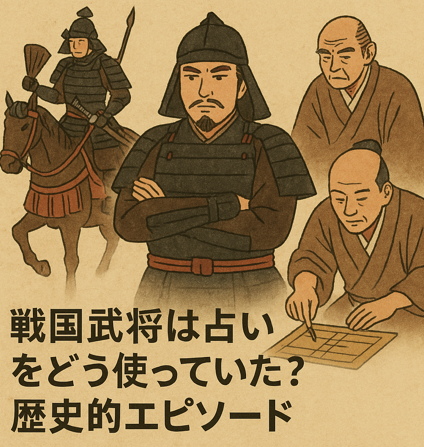
▲出陣前、軍配を手に占いを行う武将たちの様子。戦いの前には「天の兆し」を読むことが重要とされた。
はじめに:戦国時代と「見えない力」への信仰
戦国時代の武将たちは、戦略や兵法だけでなく、「運」や「天の意志」を重んじていました。
勝敗を分ける戦の前には、星の動きや風の流れ、方角を読み、出陣日を決める——。
そんな「占い」は、単なる迷信ではなく、国の命運を握る意思決定の一部だったのです。
軍配者(ぐんばいしゃ)とは?
合戦の吉凶や天候を占い、将軍に進言したのが「軍配者」と呼ばれる専門職です。
彼らは、陰陽道・易・星占いなどを使って、出陣の時期や進軍方向を決めました。
戦国の合戦には、必ずといっていいほどこの「軍配者」が同行していたとも言われています。
武田信玄と「易占」の活用
甲斐の虎・武田信玄は、政治や戦において易(えき)を重視した武将として知られています。
伝承によると、信玄は出陣の前に必ず易を立て、兵の動きや敵の出方を占ったとされます。
また、家臣の中には「人の手相を読む者」もいたと伝えられ、信玄が敵将の筆跡や印影から性格を分析した、という話も残っています。
まさに「心理戦」と「占術」を組み合わせた先駆けとも言えるでしょう。
大友宗麟と“出陣の占い”
豊後国(現在の大分県)の大名・大友宗麟は、出陣の際に占い師・角隈石宗に判断を求めたと記録されています。
そのとき、石宗は「凶」と占い、出陣を止めるよう進言しましたが、宗麟はこれを無視して出陣し、結果は敗北に終わりました。
この逸話は、占いを無視すると運命が傾くという教訓として今も語り継がれています。
織田信長と占いへの懐疑
一方で、織田信長は「占いを信じなかった武将」として知られます。
合理主義的な性格の信長は、「占いは人を惑わす」として占術を否定したと伝わっています。
ただし、戦略的演出として「吉日」を選び、家臣や民心を掌握するために利用したとも言われます。
つまり、信長は「信じないふりをして、うまく利用した」タイプだったのかもしれません。
家康と閑室元佶:関ヶ原の“運命の占い”
関ヶ原の戦いに臨む際、徳川家康は僧侶・閑室元佶(かんしつ げんきつ)を伴い、戦の吉凶を占わせました。
その結果「吉」と出たことで家康は迷いなく開戦し、天下統一への道を進んだと伝わります。
このように、**占いは戦略を後押しする「精神の支柱」**として機能していたのです。
まとめ:占いは“信念を支える戦略”だった
戦国武将たちにとって、占いは単なる迷信ではなく、己の決断を支える指針でした。
結果がどうであれ、「天命を受け入れる」という信念が、彼らの強さを作っていたのです。
現代に置き換えれば、占いはビジネスや人生の「方向性を見つめ直す」ためのツールといえるでしょう。


